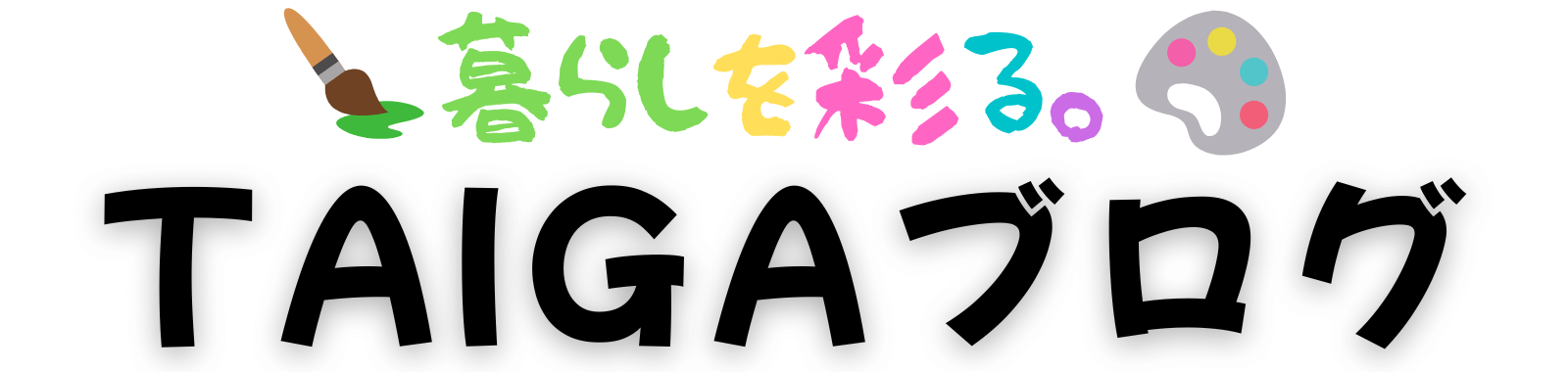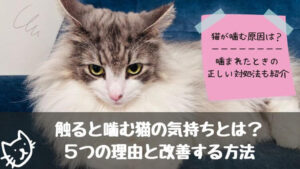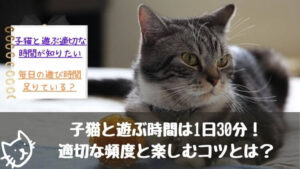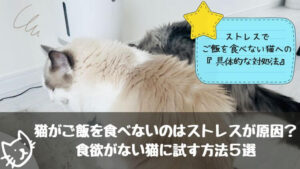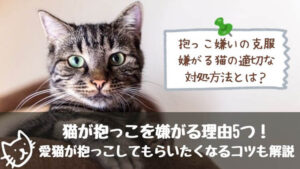当記事はこんな方におすすめ!
- 猫のブラッシングの頻度を知りたい
- 猫にブラッシングすると得られる効果は?
- 猫用のお手入れブラシはどんな種類があるの?
猫のブラッシング頻度は、どのくらいがベストなのか気になったことはありませんか?
正しくお手入れをすることで猫の健康を守ることに繋がるため、定期的なブラッシングはとても大切です。
ここでは、猫のブラッシング頻度や効果、ブラシの種類について紹介しています。
猫のブラッシングは毎日必要か?
ブラッシングの頻度は、
- 長毛種で1日1回~2回
- 短毛種は毎日~最低でも週3回
のお手入れが目安となります。
毛が絡みやすい長毛種の猫は、毎日お手入れをしてあげると毛ツヤも良くなり、毛玉もできにくくなりますよ。
猫の体調に問題がなければコミュニケーションをとるために軽めのブラッシングを毎日行うのが理想的です。
猫の換毛期について
この時期になると猫の抜け毛はすさまじく、からだについている余分な被毛を取り除かなければ、床は毛だらけに。
猫が毛づくろいの際に多くの被毛を飲み込むと、体内に入った毛玉を排出しにくくなることもあります。
抜け毛の多い時期には、「スリッカーブラシ」や「アンダーコート用ブラシ」を使い、たくさんの毛を取り除くようにしましょう。
猫ブラシでお手入れをすると得られる効果
毛並みが整う
綺麗好きな猫は体を清潔に保つために、毛づくろいをすることが日課です。
猫が自分で舐めて毛づくろいをできる部分は限られているので、届かないところは飼い主がケアをしてあげましょう。
猫の被毛はホコリや抜け毛をまといやすかったり毛と毛が擦れることによっても毛玉は発生したりします。
 mashiro
mashiro長毛種の猫は毎日ブラッシングをしないと、毛は絡みやすく毛玉ができやすい!
定期的なブラッシングは汚れを落とし、毛の絡まりを抑えてくれます。
皮膚に適度な刺激を与えることで新陳代謝が良くなり、健やかな毛並みを保つことができますよ。
余分な抜け毛を減らし健康を維持する
ブラッシングの頻度が少ないと、毛づくろいをしたときに多くの毛を飲み込んでしまうことになります。



通常は、猫の体内でかたまり(ヘアボール)を吐き出すか、便と一緒に排出されます。
体力や免疫力が十分ではない猫、子猫や高齢猫は自力で吐き出せないことがあるため、ブラッシングで余分な毛を取り除いてあげましょう。
また、ブラッシングで猫と触れ合うと、異変にも気づきやすくなり、皮膚の状態や病気の早期発見ができるかもしれません。
ブラシでお手入れをするときは、猫の体をチェックしてみることをおすすめします。
ブラッシングの時間で猫と信頼関係を築く
親しい猫同士ではお互いに被毛で舐め合う「アログルーミング」を行います。



毛づくろいできないところを互いに助け合っているよ!
人が猫に行うブラッシングも、猫にとってはアログルーミングに似た行為です。
お手入れをしてあげることで猫との信頼関係を築くことができるでしょう。
猫は飼い主さんを信頼していれば、「程よいスキンシップ」がストレス解消になります。
反対に猫が機嫌の悪い時や無理にブラッシングをしようとすれば、苦痛な時間にしかなりません。
猫の様子に配慮しながら、お互いにとって良いコミュニケーションの時間になるようにしましょう。
猫ブラシの種類はどんなものがあるの?



自分の猫にどのブラシを選んだら良いんだろう?
猫用ブラシは種類がとても豊富です。
被毛を取り除くブラシは、「長毛種用」「短毛種用」とパッケージに書かれています。
初めてブラシを用意する場合は、愛猫の長さに合わせたブラシを選びましょう。
また、「とにかくムダな毛を取り除きたい」とか、「もう少し毛艶を良くしてあげたい」などの目的もあると思います。
ブラシの素材や形状によって機能が異なりますので、目的別に合わせて使い分けをしましょう。
肌にやさしい/マッサージ効果/ムダ毛をとる
ラバーブラシ/シリコンブラシ
ラバーブラシやシリコンブラシは、やわらかくて肌あたりがよく皮膚に刺激が感じにくいので、肌の弱い子猫や高齢猫、ブラッシングが苦手な猫におすすめです。長毛種よりかは短毛種の子に適しています。
ブラシでとかせば粘りのあるゴムやシリコンで浮いている余分な毛を絡めとることができます。ブラシも洗いやすく、お手入れ簡単なのが特徴です。手にはめて猫を撫でながら余分な毛をとる「グローブタイプ」もあるので、警戒心が強い子にも人気です。
毛の量が多い子にも!絡まる毛を整えたい
ピンブラシ
毛が絡まったり、もつれが気になるときにはピンブラシを使いましょう。
ピンブラシは基本のブラシで長毛種・短毛種どちらにも使いやすいです。ブラシのピン一本、一本にすきまがあることで毛がブラッシングしたときにひっぱられづらく、毛量の多い猫にもおすすめです。ピンの先端に丸い玉がついているものは、肌当たりが良いのでブラシの扱いに慣れていない方も安心して使用することができます。
毛の絡まりもほぐしたいけど、余分な毛をたくさん除去したい
スリッカーブラシ
これ一つあれば、毛の絡まりと余分な毛を除去できるのでとっても便利なブラシです。
特徴としては、びっしりと細かい針金状のピンになっていて、毛の流れにそってブラシをかけてあげることで毛並みを整えながら、余分な毛を十分にからめて取り除くことができます。
スリッカーブラシはピンの長さで「短毛種用」と「長毛種用」が分かれています。ピンが短いものが短毛種用、長いものが長毛種用です。
毛並みをツヤツヤに仕上げたい
獣毛(天然毛))ブラシ
毛をツヤツヤに仕上げたいときは獣毛ブラシを使います。
水分と油分を含む豚や猪の毛でつくられているので、静電気がおきにくく、しっかりブラッシングすることで毛にツヤを与えることができます。余分な毛をたくさん取り除くというよりも、抜け毛のケア後やコミュニケーション目的で使用するのが良いでしょう。
毛並みを揃える/小さな毛玉をほぐす
コーム
スリムなコームタイプは毛玉をほぐす時やからだの部分使いに適しており、ブラッシングの仕上げに最適です。
コームひとつで細目と粗目の半分ずつに分かれているものが多く、顔まわりやおしりまわりなど場所や毛の状態に合わせて使い分けをします。のみがいた場合は細目の部分ですくうことも可能です。
とにかくムダ毛をたくさん除去したい
アンダーコート用ブラシ
大量の抜け毛が出てくる換毛期には、手早くムダ毛を処理できるアンダーコート用ブラシをおすすめします。
猫の毛は、表面に生えている「トップコート」と地肌の近くに生える「アンダーコート」に分かれています。アンダーコート用ブラシを使うことで、他のブラシよりも格段に毛を除去することができるんです。
しかし、ブラシでとかせばとかすほど毛がとれてしまいます。必要な毛までとらないよう、やりすぎには注意しましょう。
猫のブラッシングは毛根から毛先へ向かうように、毛の流れに沿いながら優しく丁寧にが基本!
猫のブラッシングで困ること
猫がブラッシングを嫌がるときは
猫にブラッシングを行なうときは、タイミングが重要です。
- リラックスしているとき
- 飼い主さんに甘えてくるとき
猫が落ちついている時にブラッシングをしましょう。
嫌がりはじめたら、無理強いはしないことが大切です。



ブラッシングのときに、耳やしっぽがしきりに動き始めたら嫌がりはじめているサインだよ。
猫が触れられて嫌な場所は、神経の密集しているしっぽや足先、急所のおなかです。
猫に毛玉ができてしまったら・・・
特に長毛種の猫はブラッシングをしないことで毛が絡まり、毛玉もできやすくなります。
毛玉の大きさ、状態にもよりますが、毛玉がもつれるほど地肌がひっぱられて猫に痛い思いをさせてしまいます。
猫のからだに毛玉をみつけたら、大きい塊になる前にほぐしましょう。
毛玉をほぐす順番は以下のように行います。
- 毛玉になっている部分をつまみ他の毛が引っ張られないようにします。
- ピンブラシかスリッカーブラシでつまんでいる毛玉をやさしくほぐしていきます。
- ある程度ほぐしたら、コームで細かくとかして毛を整えます。
まとめ


- 猫にブラシをかけてあげることで、毛玉ができる前に毛の絡みやもつれを抑えることができる
- 猫のからだについている抜け毛や、ムダ毛をブラシで取り除いておけば体内に入る毛の量を抑えることができ、猫の健康を維持することにつながる
- 猫用ブラシは大きく分けて長毛種用、短毛種用があり目的別に使い分ける
- ブラッシングの頻度は長毛種、短毛種どちらも毎日が理想的
- 猫の換毛期はとくにしっかりとお手入れで余分な毛を取り除いてあげる。
(換毛期は、春と秋頃の2回やってくる)
ブラッシングは猫との大切なスキンシップの時間です。
毎日、数分のお手入れで愛猫の健康を守りながら信頼関係を築いていきたいですね!