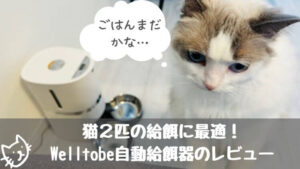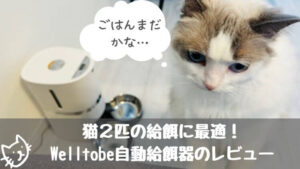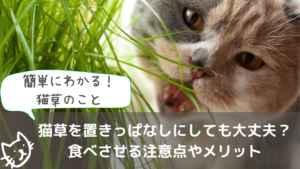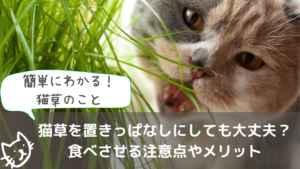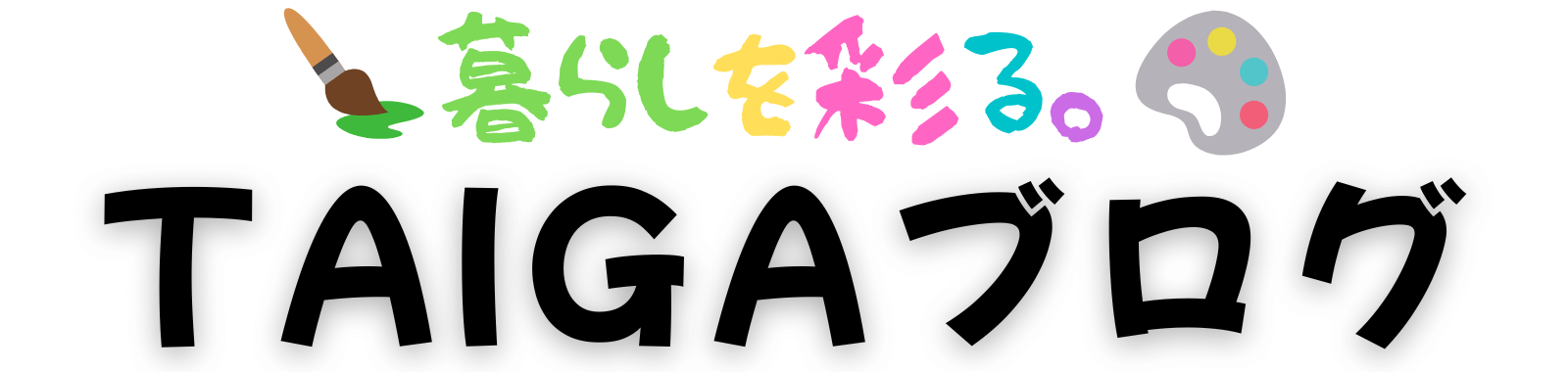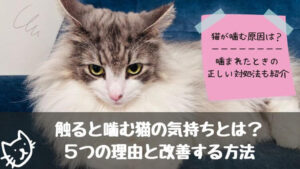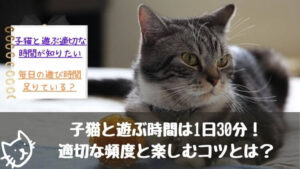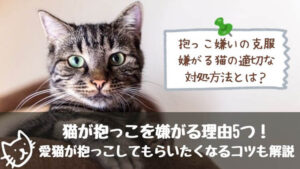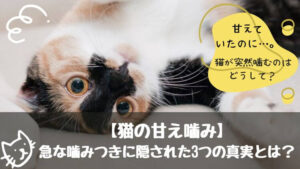当記事はこんな方におすすめ!
- 猫がきちんと食べてくれるか心配
- コストパフォーマンスに納得できるか不安
- 自動給餌器の誤作動なく使うことはできる?
「愛猫には毎日決まった時間にご飯をあげたい!」そんな思いで自動給餌器を導入したものの、「思っていたのと違う…」と後悔する飼い主さんも少なくありません。
確かに便利なアイテムですが、実際に使ってみると気づく意外な落とし穴もあるのです。
この記事では、猫用自動給餌器で失敗しやすい3つのデメリットとその対策をわかりやすく解説します。
それでは、ご参考までにどうぞ
「猫の自動給餌器」便利だけど後悔することも?

忙しい毎日でも愛猫にきちんとご飯を与えられる「自動給餌器」。
タイマー機能やスマート給餌機能などが魅力ですが、お家に導入したことで「失敗した」と感じるのはどうしてなのでしょうか。
デメリットを先に理解しておけば、愛猫も飼い主さんも毎日の生活が今までよりも快適になり、メリットも感じることができますよ。
1. 故障や誤作動のリスクがある

自動給餌器は機械なので、どうしても故障や誤作動のリスクがあります。
とくにバッテリー切れやタイマー機能の不具合で、予定通りにフードが出ないことも。
長時間留守にする場合、気づかないうちに猫が空腹でストレスを感じてしまうこともあります。
 mashiro
mashiroいざ故障すると困るものです。
ただ、不具合に関しては、評判の良い自動給餌器を選んでおけば、頻繁に故障することは少ないでしょう。
自動といえど、飼い主さんが普段から、猫の自動給餌器が作動していることを確認できていれば心配しすぎなくても大丈夫です。
問題は、通常はコンセントから電源をとる自動給餌器は停電などで作動しなくなってしまうケースが考えられること。
自動給餌器を選ぶ際は、停電などのもしものときに電源が切れてしまわないように、電池を入れられるものやバッテリー式のタイプを選ぶことをおすすめします。
故障や誤作動のリスク対策
定期的に動作確認を行い、特に長期間不在にする前は念入りにチェックすること。また、電源以外でも作動する製品を選ぶと安心です。
おすすめはコチラ!
2. 猫の健康管理が難しくなる


自動給餌器は決まった量のご飯を自動で出してくれる一方で、猫の食欲や体調の変化に気づきにくくなることがあります。
たとえば、 猫がご飯を食べる時間帯別で見たときに食べる量に変動があっても気付きにくいことがあるのです。



自動給餌器を使用していることで「食べているはず」と思い込み、異変に気づくのが遅れることも。
猫の食欲不振は病気の初期サインであることが多いので、早期発見が重要になります。
設定した給餌量が間違っていないか確認することや、
朝晩など、飼い主さんが確認する時間を決めて自動給餌器のお皿にフードがどれくらい残っているかのチェックをしてあげることが大切です。
猫の体調不良のサインを見逃さないように注意してあげましょう。
猫の健康管理対策
自動給餌器内にフードが少なくなっていないかの確認は定期的に行いましょう。食事の様子を確認できるカメラ付きの製品を選ぶとより安心ですね。
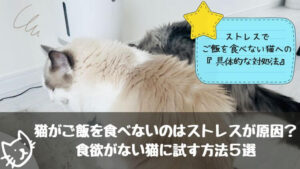
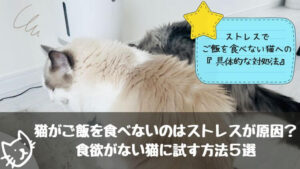
3. コミュニケーション不足になりやすい


給餌は猫との大切なコミュニケーションの時間です。
しかし食事が自動化することで、「食事=ふれあいの時間」が減り、猫との絆が薄くなる可能性もあります。
とくに甘えん坊の猫は、飼い主とのふれあい不足からストレスを感じることもあるでしょう。



便利だけど、温かみが感じないかも。
コミュニケーション不足への対策
ご飯の時間以外で猫としっかり遊ぶ時間を確保することが大切です。また、手動給餌と自動給餌を組み合わせ、バランスよくふれあいの機会を作りましょう。
まとめ


自動給餌器は忙しい飼い主の強い味方ですが、便利さの裏にはデメリットも存在します。
故障のリスク、健康管理の難しさ、コミュニケーション不足といった課題を理解した上で、定期的な点検や愛猫とのふれあい時間を大切にすることで、後悔しない使い方ができます。
自動給餌器は確かに便利なアイテムですが、愛猫の健康や幸せを守るためには、飼い主の細やかな配慮が欠かせません。
定期的な動作確認や健康チェック、猫の心身のケアを行えば自動給餌器のメリットを最大限に活かすことができるでしょう。
愛猫との絆を深めながら、快適で安心できる環境を整えていきたいですね。